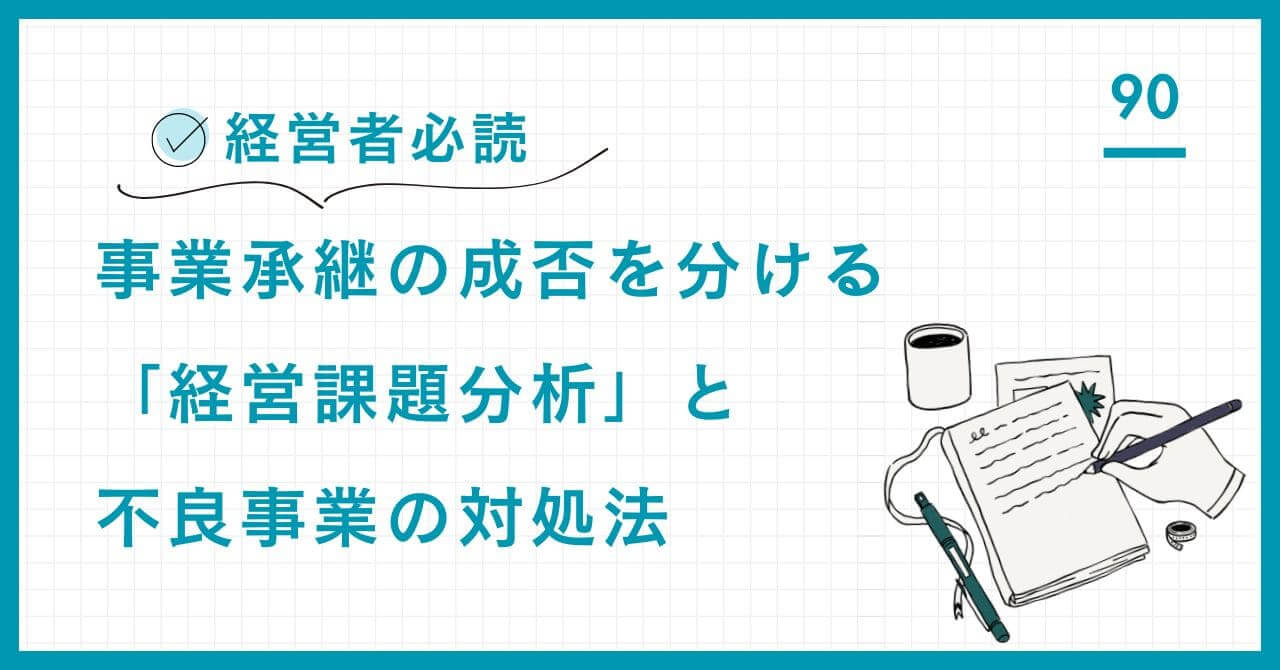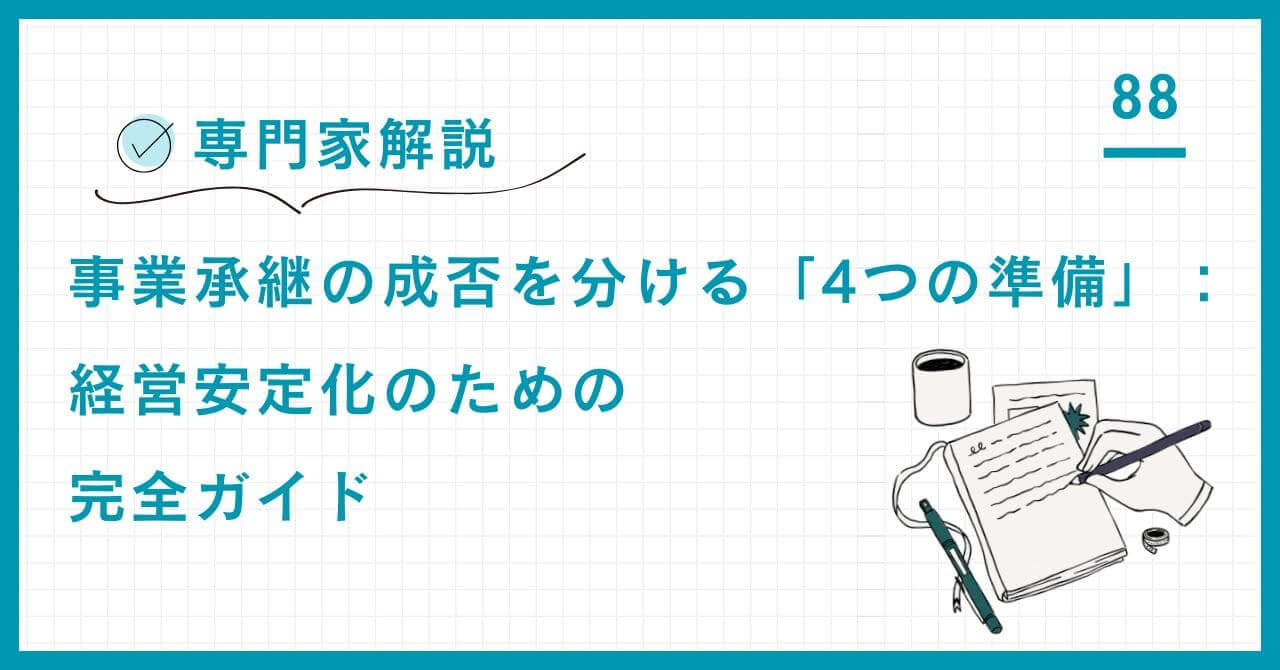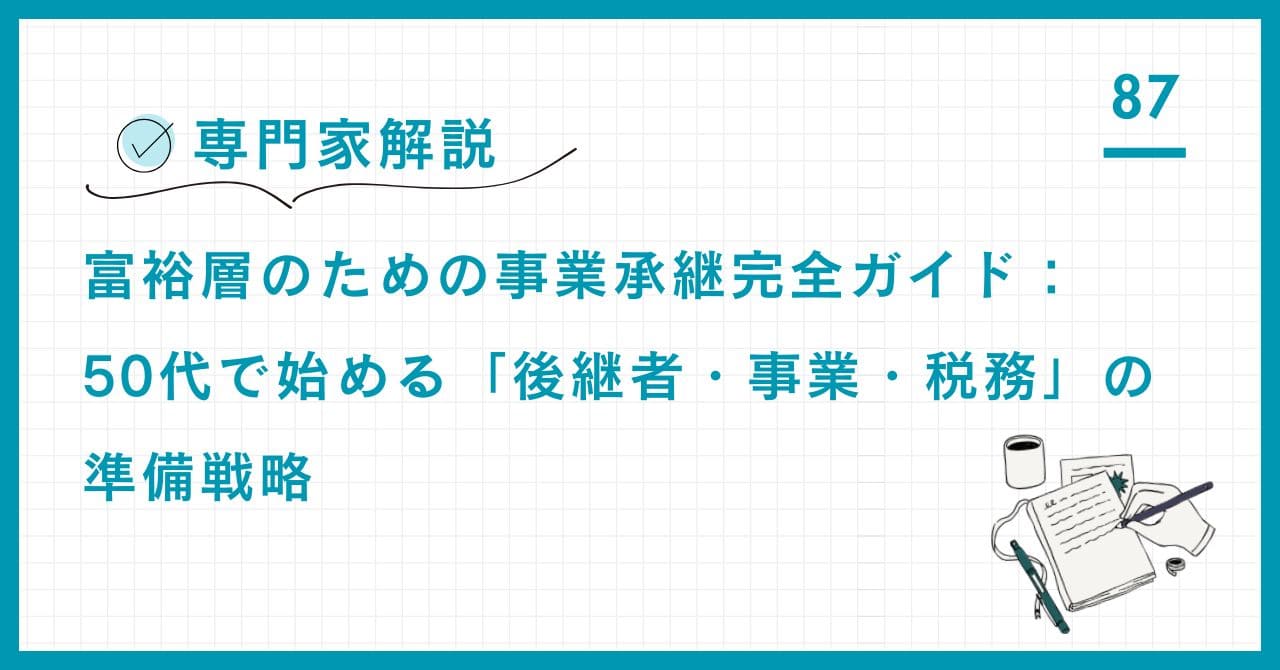事業承継の最大の目的は、「会社を存続させ、後継者が経営できる“良い状態”を引き継ぐこと」です。
ところが現場では、自社の経営課題を十分に分析しないまま、赤字部門や採算の合わない事業、不良資産を抱えたまま事業承継を行ってしまうケースが少なくありません。
現経営者にとっては思い入れのある事業であっても、改善の優先順位があいまいなまま承継すると、後継者は就任直後から重い荷物を背負うことになります。その結果、経営改善の打ち手が後手に回り、資金繰りの悪化、信用力の低下、人材流出などの悪循環を招き、最悪の場合は廃業に至るリスクさえあります。
本記事では、
- 経営課題の分析が事業承継の成功率を左右する理由
- 不良事業を残した企業と、整理してから承継した企業の明暗
- 3C・SWOT・5フォースなどを用いた、実務的な分析・対処の進め方
を、専門家の視点からわかりやすく解説します。
[ 目次 ]
1. 事業承継前に経営課題の分析・削減を行う戦略的メリット
経営課題の分析と不良事業の削減は、本来であれば事業承継の有無にかかわらず、会社の成長のために不可欠な取り組みです。
しかし「事業承継前」というタイミングで実施することで、特に大きな戦略的メリットが生まれます。
1-1. メリット1:会社の長期的な存続と成長の促進
不良事業とは、継続しても会社全体の利益やキャッシュフローに貢献せず、むしろ経営に悪影響を与えている事業のことです。
こうした不良事業を長期間放置すると、収益や資金繰りはじわじわと悪化し、最悪の場合には経営破綻・廃業に追い込まれるおそれもあります。
- 効果:事業承継前の段階で不良事業を削減しておくことで、
・会社全体の収益性・財務体質が改善される
・後継者が引き継いだ後、「伸ばすべき成長事業」に経営資源を集中できる
という形で、会社の長期的な存続と成長の可能性を高めることができます。
1-2. メリット2:後継者の経営リスクの排除
事業承継では、長年会社を牽引してきた経営者に代わり、新たな後継者が経営のかじ取りを担います。
一般に、後継者は現経営者ほどの経験や判断力をまだ備えていない段階でバトンを受け取ることが多く、複雑な不良事業の整理を一人で担わせるのは現実的ではありません。
- 意義: 事業承継前という“時間的ゆとり”のある段階で、不良事業の削減や整理を済ませておくことは、
・経営経験が浅い後継者に、過度なリスクと負担を背負わせない
・後継者が「攻めの経営」に集中できる土台をつくる
という意味で、現経営者が果たすべき重要な役割の一つです。
まとめ:事業承継前の経営課題の分析は、会社の長期的な存続と成長を促し、経験の浅い後継者の経営リスクを排除するための、最も重要な土台作りです。
2. 経営課題の分析・不良事業の削減を行う具体的な手法(HowTo)
経営課題を正しく把握し、不良事業を特定するためには、「勘と経験」だけではなく、論理的なフレームワークを活用することが欠かせません。
2-1. 【STEP 1】自社の状況に相応しい分析手法の採用
経営課題を分析する方法には、以下の主要なフレームワークがあります。自社の状況に相応しい手法を採用するか、組み合わせて採用するとより効果的です。
- 3C分析: 顧客・競合他社・自社の観点をもとに分析し、自社の成功要因を探ります。
- SWOT分析: 強み・弱み・機会・脅威という4つの視点から、業界の内部環境と外部環境を分析します。(ケーススタディのA社が採用)
- 5フォース分析: 売り手・買い手・競争業者・新規参入業者・代替品という5つの競争要因をもとに、業界の外部環境を分析する手法です。
2-2. 【STEP 2】不良事業の「再建」か「撤退」かの決定
分析の結果、問題のある事業が特定できたら、次のステップはその事業を「再建するのか」それとも「撤退するのか」を決めることです。
- 再建の余地があるのか
- 再建に必要な時間・コストに見合う見込みがあるのか
- 事業承継までに必要な対応を終えられるのか
といった観点から冷静に判断します。
再建が困難である場合や、承継までの時間が限られている場合には、前経営者の責任として「撤退」を決断することも、会社と後継者を守るうえで合理的な選択となります。

2-3. ケース比較:分析の有無が分けた明暗
- 成功事例(A社):不良事業を見極めて撤退し、成長事業に集中
A社は、主力の「電気ポット製造」に加え、「アイロン機器製造」という不良事業を抱えていました。
A社は事業承継前に時間をかけてSWOT分析を実施し、アイロン機器製造は構造的に収益性が低く、今後も成長が見込めない「弱み」であると判断。
事前に撤退を決断し、経営資源を成長性の高い電気ポット事業に集中させました。
その結果、承継時の売上高は、ピーク時の120%にまで増加。
後継者は、好調な事業に経営資源を集中できる、非常に良好な状態で事業を引き継ぐことができました。
- 失敗事例(B社):分析不足により、撤退する事業を誤ったケース
一方B社は、十分な経営課題の分析を行わず、短期間で結論を出してしまいました。
その結果、本来は見直すべき別事業があったにもかかわらず、「掃除機製造」を弱みと誤認し、撤退を決定。
本当に撤退すべき不良事業を残したまま、成長余地のあった事業を手放してしまったのです。
その後、売上高はさらに低下し、後継者は就任直後から深刻な赤字の立て直しを強いられることになりました。
まとめ:経営課題分析は、手法を問わず「時間をかける」ことが重要です。誤った分析は、失敗事例のように、本来の成長事業を見誤る致命的な結果を招きます。
3. まとめ:事業承継の成功は「万全の体制」から始まる
2つの事例の比較からも分かるとおり、会社を存続・成長させるうえで、事業承継前における経営課題の分析・不良事業の削減は非常に重要な行為です。後継者にスムーズに事業を引き継いでさらなる会社の成長につなげられるよう、前経営者として果たすべき役割を果たし、万全の体制のもとで事業承継を迎えましょう。
なお、事業承継を進める際は、以下の「3つの原則」を守って正しく進めていきましょう。
- 独断では行わない
- 複数の専門家から意見を集約し判断する
- 時間をしっかり掛けて対応する
【関連記事:【専門家解説】富裕層のための事業承継完全ガイド:50代で始める「後継者・事業・税務」の準備戦略】