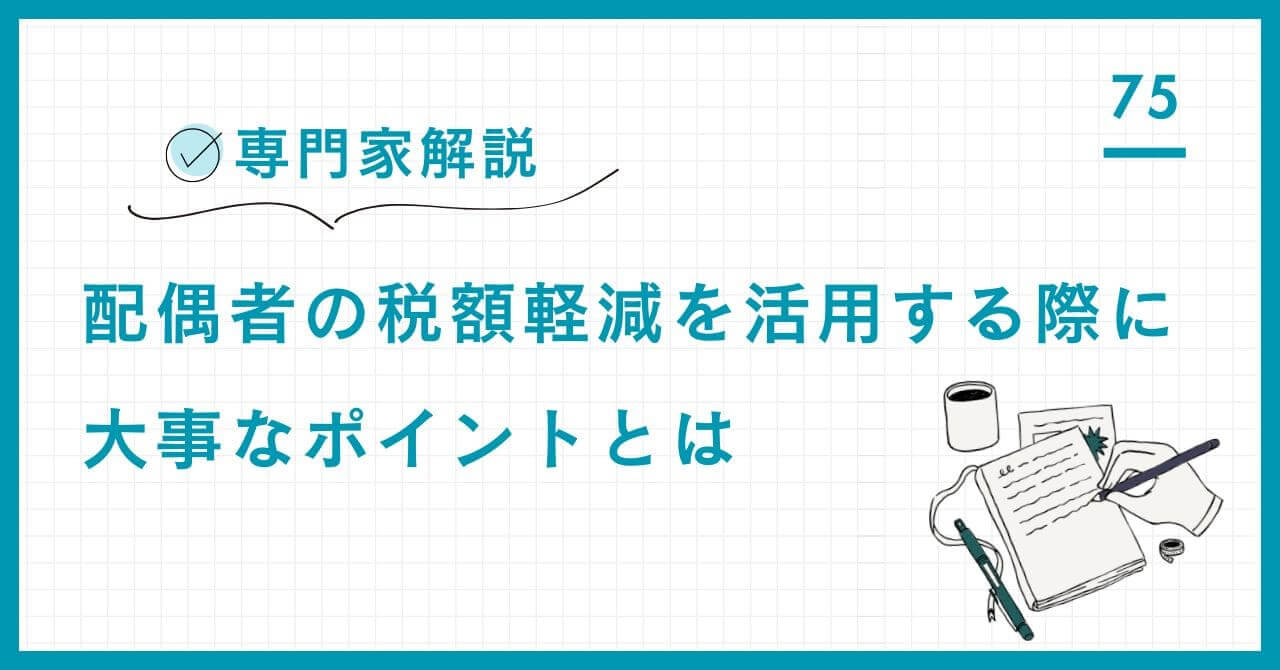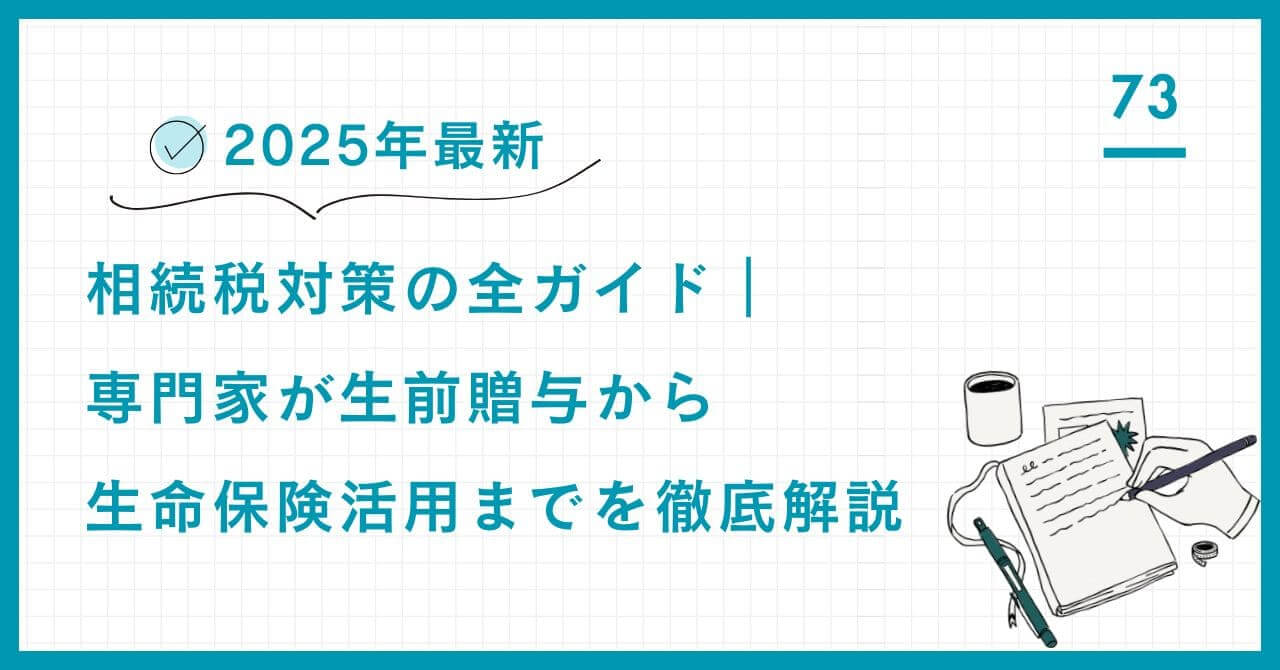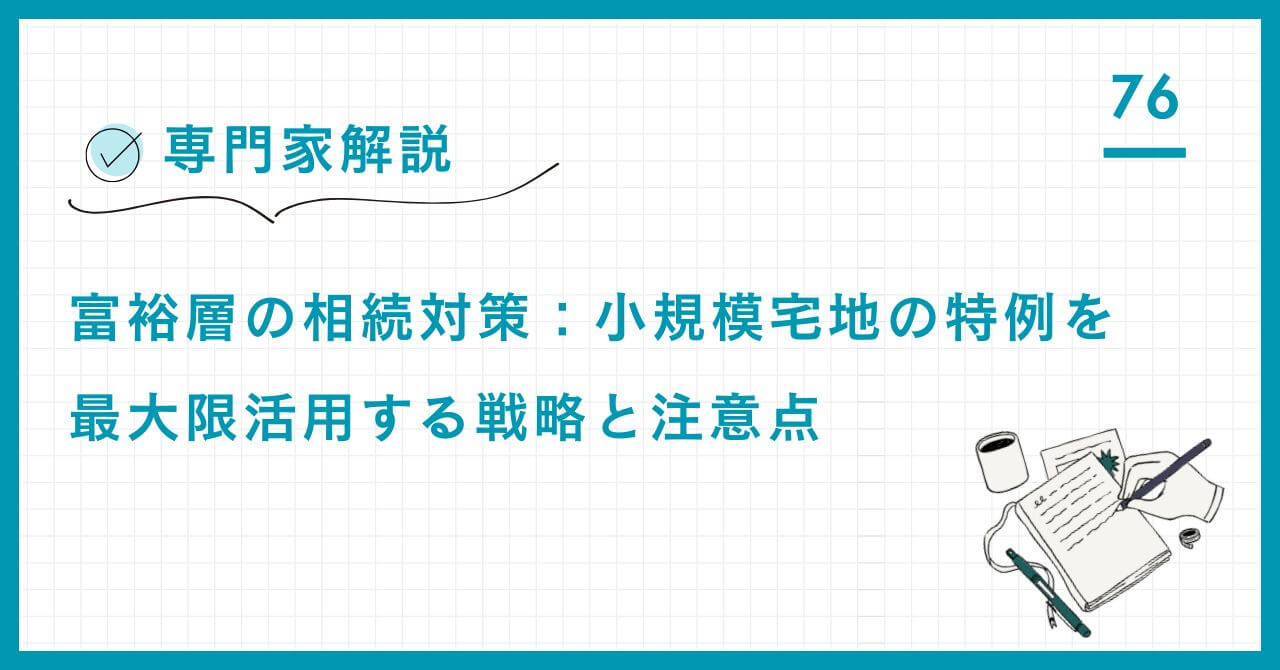夫婦間の相続において、相続税の負担を大きく抑えることができる制度として「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」があります。相続財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までについては、計算上相続税がかからなくなるため、一次相続(最初の相続)における税負担を抑える強力な制度といえます。
その一方で、十分な計画を立てずに「とりあえず全部を配偶者へ」と相続させることは、将来の二次相続(配偶者死亡時)で税負担が増えるリスクを高める可能性があります。本記事では、制度の仕組みと注意点を整理しつつ、二次相続まで見据えて家族全体の税負担を最適化する考え方を解説します。
[ 目次 ]
1. 配偶者の税額軽減の仕組みと「二次相続リスク」
配偶者の税額軽減は、配偶者の生活保障を目的とした制度であり、相続財産の一定額まで相続税が非課税になる優遇措置です。しかし、この特例のフル活用は、必ずしも家族全体の利益になるとは限りません。
1-1. 制度の概要と目的
配偶者の税額軽減は、配偶者の生活保障を目的とした制度であり、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで、配偶者に相続税が課されないように調整する仕組みです。
この制度により、一次相続において配偶者が相続税を支払わないケースは多くみられます。
相続税の基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
1-2. 二次相続リスクが生じやすい理由
一次相続で配偶者が多くの財産を取得すると、二次相続時の課税対象が減らないため、以下の2点が重なり税負担が増加する可能性があります。
- 二次相続においては配偶者控除が使えない
- 相続人が子のみとなり、基礎控除額が小さくなる
これにより、一次相続では税金がかからなくても、結果的にトータル課税額が増えるケースが生じます。
2. 【シミュレーション】一次相続で1,440万円の節税を実現する方法
ここでは、具体的なシミュレーションを通じて、配偶者へのフル活用と、子どもへの計画的な配分が、二次相続の納税額にどう影響するかを検証します。
【シミュレーション条件】
- 財産の総額: 父親の財産 1億6,000万円、母親の財産 4,000万円
- 法定相続人: 母親(配偶者)、子ども2名(合計3名)
2-1. シナリオA:配偶者の税額軽減をフル活用した場合
一次相続で配偶者の税額軽減をフル活用し、すべてを母親が相続したと仮定します。
| 相続段階 | 課税される財産(概算) | 納税額 |
| 一次相続(父 $\rightarrow$ 母) | 1億6,000万円(全額、配偶者控除適用) | 0円 |
| 二次相続(母 $\rightarrow$ 子2人) | 2億円(父の財産1.6億円+母の財産0.4億円) | 3,340万円 |
| 合計納税額 | 3,340万円 |
2-2. シナリオB:一次相続で子どもに法定相続分を配分した場合
一次相続で、子どもたちに法定相続分を相続させ、母親は配偶者控除の範囲内で財産を相続したと仮定します。
| 相続段階 | 課税される財産(概算) | 納税額 |
| 一次相続(父 $\rightarrow$ 母・子) | 1億6,000万円から基礎控除後の課税価格 | 740万円 |
| 二次相続(母 $\rightarrow$ 子2人) | 1億2,000万円(父の財産8,000万円+母の財産4,000万円) | 1,160万円 |
| 合計納税額 | 1,900万円 |
3. 賢明な資産配分戦略:二次相続を見据えた専門家の視点
なぜ、一次相続で配偶者の税額軽減をフル活用すると、二次相続の税額が大幅に増えてしまうのでしょうか。その理由は、「税率の仕組み」と「基礎控除額の減少」という2つの要素にあります。
3-1. 相続税の「累進課税」が招く増税リスク
相続税は、相続財産が増えれば増えるほど税率が高くなる累進課税の仕組みをとっています。
- 要因: 一次相続で財産を子どもに相続させないと、二次相続の相続財産が増え、より高い税率が適用されます。財産を二つの相続に分散させ、低い税率で課税することが、家族全体の税負担を減らす基本戦略です。

3-2. 専門家が推奨する「バランス」の取り方(Q&A形式)
Q: 設例のように、一次相続で子どもに相続させなかったら必ず二次相続の税額が増えますか?
A: 必ずしもそうとは限りません。相続税には、小規模宅地等の特例など、二次相続に向けて活用できる節税のためのスキームがいくつも存在します。一次相続で配偶者の税額軽減をフル活用したとしても、二次相続に向けて専門家による長期的な対策(例:生前贈与、信託の活用)さえしておけば、二次相続の税額を減らすことは十分に可能です。
Q: 財産を分ける際、配偶者はいくら相続するのが最適ですか?
A: 配偶者は、「配偶者の税額軽減」の非課税枠の範囲内で、二次相続まで見据えた最適な金額を相続すべきです。ただし、子どもに相続させる財産は、将来的な納税資金や、生活資金に充てる現預金など、何に使うかを明確にした上で配分することが重要です。
4. まとめ:賢明な資産承継は「二次相続まで見通す」プランニングから
配偶者の税額軽減は強力な制度ですが、そのフル活用は二次相続での増税リスクを伴います。賢明な資産承継は、一次相続で完結せず、「二次相続まで見通す」長期的なプランニングから始まります。
配偶者、子どもへの資産配分を戦略的に分散し、相続税を減らす特例などを最大限に活用することが、家族全体で得をする秘訣です。ご自身で判断できない場合は、節税し損ねてしまうリスクがあるため、税理士などの専門家にできるだけ早い段階で相談することをおすすめします。
【関連記事:【2025年最新】相続税対策の全ガイド|専門家が生前贈与から生命保険活用までを徹底解説】