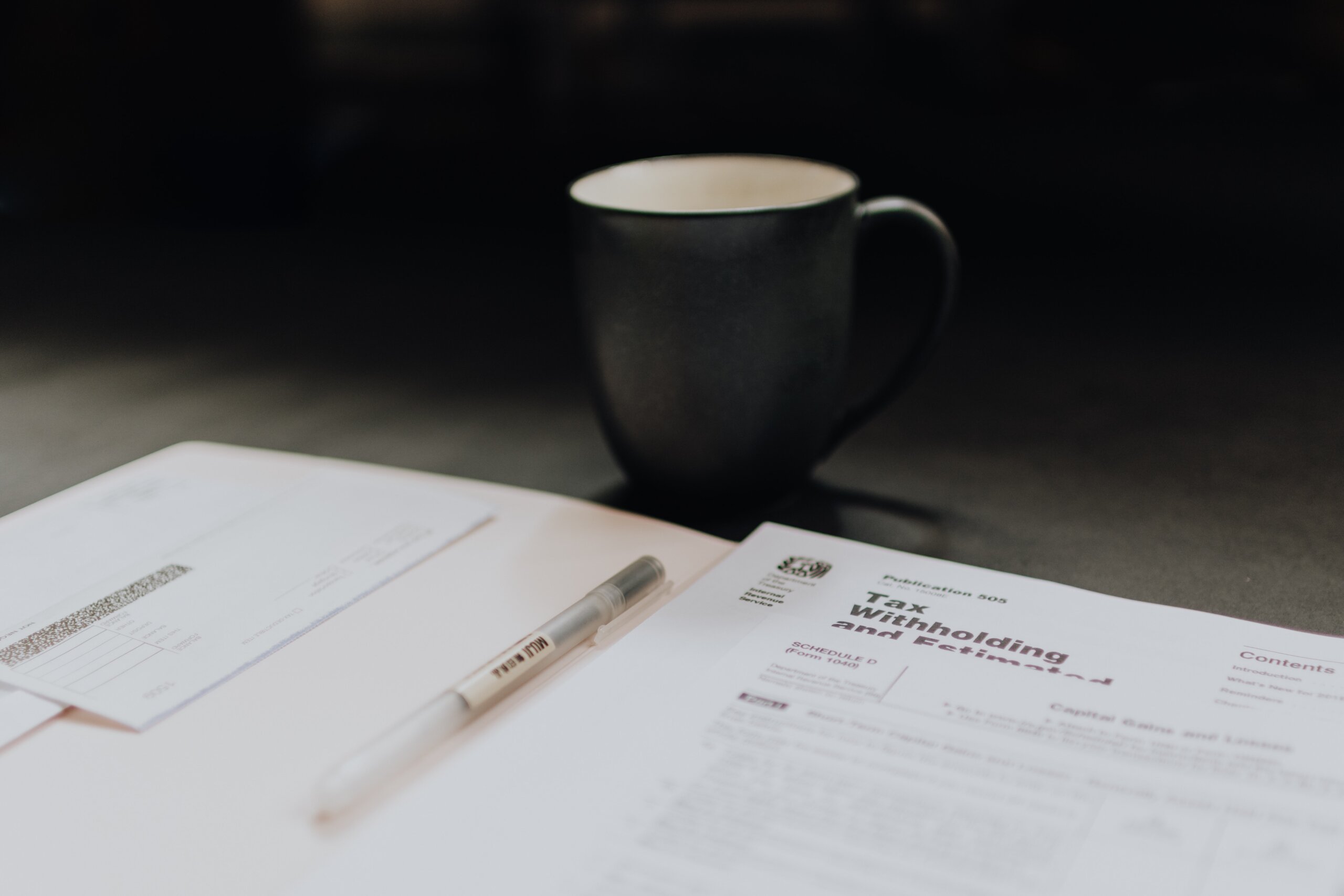仮想通貨と納税について詳しく考えてみたいと思います。
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて
仮想通貨の取引があり、もうかった場合には、利益の部分は税金の課税対象となります。確定申告の時には申告洩れが生じないように注意する必要があります。
しかし、昨今の仮想通貨の市場を見ていると、相場は下落している感があり、仮想通貨の保有者でもうかっている人は非常に少ないのではないか?という印象を持っています。
国税庁は2019年12月20日に「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」(以下、「FAQ」と記載します。)という情報を更新しました。FAQには所得税の計算方法や、財産債務調書への記載方法が掲載されており、仮想通貨に関する取扱いが網羅的にまとめられています。仮想通貨をお持ちの方はぜひこちらのFAQをご覧ください。
なお、海外の閉鎖された仮想通貨交換所での取引に関する情報であっても、取引を追跡することができるのが仮想通貨の特徴です。仮想通貨はCRS情報の対象外とされていますが、取引情報を追跡され過去の仮想通貨バブルの際の申告洩れを遡って指摘されるリスクもあるのでご注意ください。
筆者がFAQを読んで大変興味をもったのは、「仮想通貨による給与等の支払」という項目です。課税上の取扱いとしては支給時の取引価額をもって、源泉徴収税額を計算するという内容です。
仮想通貨は日常生活の中で支払い手段の一つとして普及してきていることをふまえると、労働者が仮想通貨での賃金支給を期待する可能性もあると思います。しかし、仮想通貨は納税手段として認められてはいません。雇用主が源泉徴収した税額を納付する手段は日本円のみになります。
仮想通貨は貨幣?
現代貨幣理論(Modern Money Theory以下、「MMT」と略します。)では、仮想通貨は貨幣ではないとされています。その理由は、仮想通貨は額面価額を保障する中心的な発行者が存在しないことから巨大なリスクを孕んでおり、租税の支払いや借金の返済に用いることができないため貨幣とはなりえないとされています。
換言すると、貨幣制度はあくまでも国家が計算貨幣を決め、それを単位として表示される租税義務を履行するための支払い手段を発行する制度であるということになります。だから仮想通貨は貨幣でないことになります。
MMTによると、納税者が通貨を使って租税を支払えるようにするためには、まず政府が財政支出をする必要があるとされています。すると納税者は納税をするために通貨を受け取ることになり、通貨が流通することになると説いています。
政府は国債の発行により財源の確保ができます。そのため政府が租税を必要とするのは、歳入を増やすためでなく、あくまでも国民が通貨を手に入れるために生産活動を行うように仕向けるための手段ということになります。
COVID-19の影響により現実の移動に制約が課されるなかで、経済取引が現実から仮想に切り替わっていくことを予感させられる昨今において、筆者は仮想通貨の需要が高まっていくのではないかと思っています。