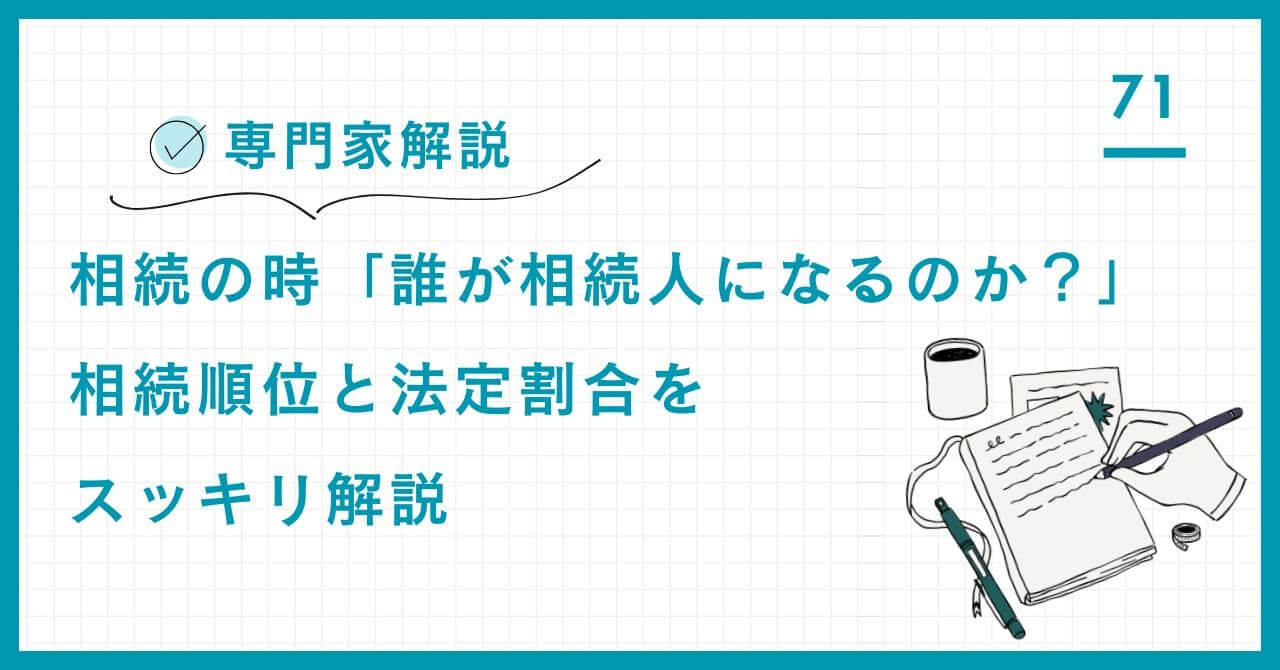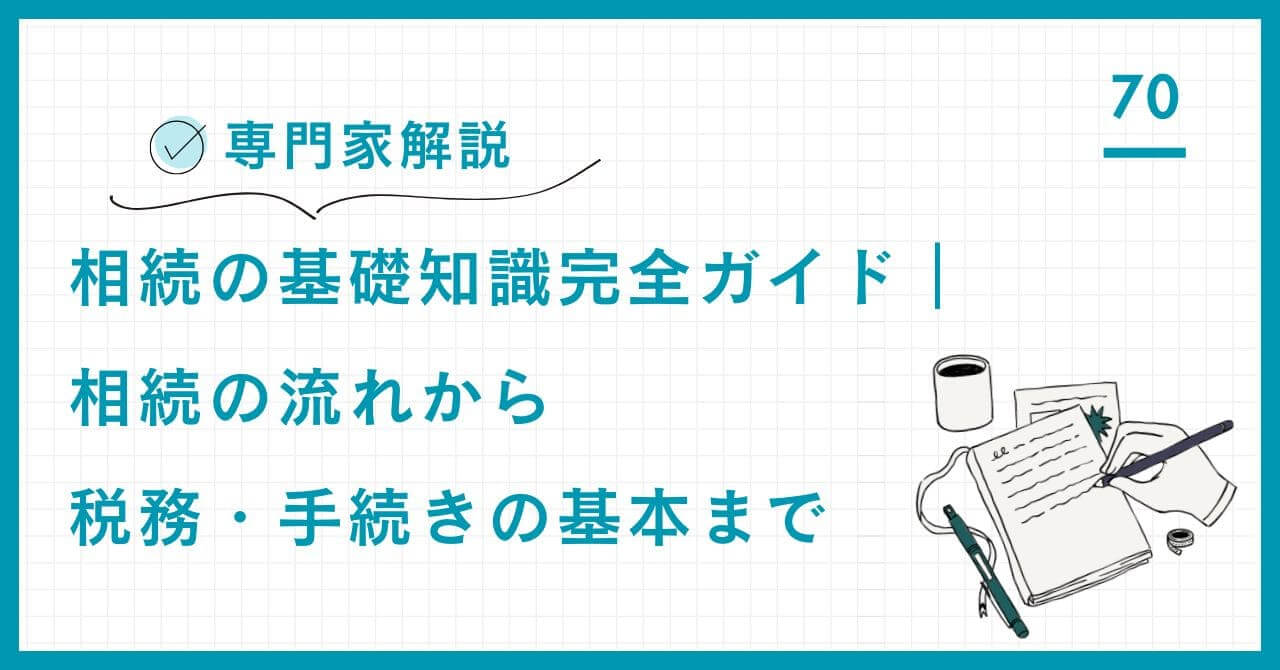相続が発生した際、まず最初に行うべきは「相続人の特定」と「法定相続分の把握」です。このルールを正しく理解していなければ、相続税の申告、遺産分割協議、納税資金の準備といったその後のすべてが滞ってしまいます。特に資産規模が大きい富裕層においては、相続人が誰になるかによって、適用される特例や税負担が大きく変動するため、法的知識は不可欠です。
本記事では、相続における誰が相続人になるのかという基礎から、遺留分といった権利関係まで、専門的かつ分かりやすい視点から解説します。この記事を読むことで、ご自身の資産承継の「設計図」の土台が明確になるでしょう。
[ 目次 ]
1. 相続人の確定ルール:「相続順位」と「代襲相続」の基礎
相続は、誰が財産を承継するかの明確なルール(相続順位)に基づいて行われます。この順位は法律で厳格に定められており、故人(被相続人)の配偶者と、血縁者のうち最も優先順位の高い者が相続人となります。相続人は常に配偶者と、血縁者のうち第一順位から順に優先される者で構成され、上位の順位がいる場合、下位の順位の者は相続人になれません。
1-1. 配偶者と血縁者の優先順位の仕組み
故人の配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。それに加え、血縁者のうち以下の順位で優先される者が相続人となります。
| 順位 | 相続人の範囲 | 具体的な続柄 | 優先順位 |
| 第一順位 | 直系卑属 | 故人の子、子がすでに亡くなっている場合は孫 | 最優先 |
| 第二順位 | 直系尊属 | 故人の父母、父母がすでに亡くなっている場合は祖父母 | 第一順位がいない場合に相続 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 故人の兄弟姉妹 | 第二順位までいない場合に相続 |
相続人の構成: 必ず「配偶者+(血縁者のうち一番上の順位の相続人)」という組み合わせになります。上位の順位の相続人が一人でも存在する場合、それより下位の順位の者は一切相続人になれません。
1-2. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)の特殊なケース
相続開始時に、本来相続人となるはずだった方がすでに亡くなっている場合、その相続人の「子」が代わりに相続人となる制度を代襲相続といいます。代襲相続は、第一順位(子)と第三順位(兄弟姉妹)において発生します。ただし、第三順位の兄弟姉妹の場合は、甥や姪までで再代襲(再々代襲)は認められていません。
2. 相続財産の「法定割合」:誰がどれだけ相続するのか?
誰が相続人になるかが特定されたら、次に財産を分ける割合を決定する必要があります。民法では、遺言書がない場合に適用される法定相続分が定められています。法定相続分は民法で明確に規定されており、相続人の構成によって割合が決まり、子が複数いる場合は子全員で残りの割合を均等に分けるのが原則です。
2-1. 相続順位ごとの配偶者と血縁者の割合
相続人の組み合わせによって、配偶者とその他の相続人の財産の分け方が以下のように明確に決められています。
| 相続人の構成 | 配偶者の法定相続分 | 血縁者の法定相続分 | 血縁者の分割方法 |
| 配偶者と子(第一順位) | 1/2 | 1/2 | 子が複数いる場合は、残りの1/2を子全員で均等に分割 |
| 配偶者と父母(第二順位) | 2/3 | 1/3 | 父母が複数いる場合は、残りの1/3を父母全員で均等に分割 |
| 配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 3/4 | 1/4 | 兄弟姉妹が複数いる場合は、残りの1/4を全員で均等に分割 |
| 配偶者のみ | すべて(1/1) | なし | |
| 血縁者のみ(配偶者なし) | なし | すべて(1/1) | 同順位の者全員で均等に分割 |
2-2. 実際の財産分割の進め方
法定相続分は、あくまで遺言書がない場合の目安となる「法律上の割合」です。実際の財産の分け方は、相続人全員が参加する遺産分割協議によって自由に決定できます。ただし、協議が難航した場合は、法定相続分が争いの基準となることが多いです。
3. 富裕層の資産承継と「遺言書」の法的効力
法定相続分が定められている一方で、故人が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書の内容が法定相続分に優先して適用されます。遺言書は、単なる財産分割の手段ではなく、資産承継の仕組みをコントロールする上で不可欠なツールとなります。
3-1. 遺言書による相続人指定の優先
遺言書には、財産を誰に、どれだけ渡すかを記載できます。故人の意思が明確に示されているため、たとえ法定相続人ではない第三者や慈善団体に「全財産を寄付する」と記載されていても、その内容が法的に優先されます。
3-2. 遺言書を活用した資産承継のコントロール
特に富裕層の資産承継においては、遺言書は単なる財産分割の手段ではなく、資産承継の仕組みをコントロールする上で不可欠なツールです。遺言書を活用することで、複数の事業用不動産や自社株を、次世代の経営者に集中させるなど、事業の安定性を優先した財産配分を指定できます。
この際、複雑な資産を扱う場合、形式不備で無効とならないよう、公正証書遺言を作成し、内容についても税理士や弁護士の助言を受ける中立的なセカンドオピニオンが極めて重要となります。

4. 感情的な対立を防ぐ「遺留分侵害額請求」の仕組み
故人の遺志を優先する遺言書があったとしても、長年故人を支えてきた家族の生活保障のために、一定の範囲内の法定相続人には最低限の相続分が保障されています。この権利が遺留分(いりゅうぶん)であり、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の取り分となります。
4-1. 遺留分が認められる法定相続人の範囲
遺留分は、法定相続人であっても第三順位の兄弟姉妹には認められていません。遺留分が認められるのは、配偶者、子(直系卑属)、父母・祖父母(直系尊属)です。兄弟姉妹が唯一の法定相続人となるケースでは、遺言書がそのまま実行され、遺留分侵害額請求はできません。
4-2. 遺留分の割合と請求の仕組み
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なり、遺産の総額に対する割合として決定されます。
| 相続人の組み合わせ | 遺産の総額に対する遺留分 |
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者 1/4、子 1/4(子が複数いる場合は均等割り) |
| 子のみ | 1/2(子が複数いる場合は均等割り) |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 1/3、直系尊属 1/6(尊属が複数いる場合は均等割り) |
| 直系尊属のみ | 1/3(尊属が複数いる場合は均等割り) |
| 兄弟姉妹のみ | なし(遺留分なし) |
遺留分侵害額請求: 遺留分が侵害された相続人は、遺言書で財産を多く受け取った者に対し、その侵害された額に相当する金銭を請求することができます。遺言書を作成する場合も、この遺留分を侵害しないよう配慮することが、トラブル回避の鉄則です。
5. 相続に関するよくあるご質問(FAQ)
5-1. Q. 死亡保険金は相続財産に含まれますか?
A. 死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象となる「相続財産」には含まれません。また、税法上、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となる優遇措置があります。これは、納税資金の確保や相続対策として富裕層に非常に活用されています。
5-2. Q. 相続人が行方不明の場合、手続きはできますか?
A. 相続人の中に連絡が取れない、あるいは行方不明の人がいる場合、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうか、失踪宣告の手続きを行う必要があります。この手続きには時間と手間がかかるため、早急に専門家にご相談ください。
5-3. Q. 自分の資産が法定相続分通りに分けるのが適切か判断できません。
A. 法定相続分は、あくまで法律上の目安です。富裕層の資産承継では、家族の価値観や事業の安定といった目的を優先し、法定相続分とは異なる配分とすることが一般的です。まずはFMS(ファミリーミッション・ステートメント)を作成し、ご自身の意思を明確にすることが重要ですし、専門家へご相談ください。
6. まとめ:相続の成功は「設計図」と「正確な知識」から
相続の成功は、「誰が相続人になるのか」「どれだけ相続分があるのか」という基礎知識を正確に把握することから始まります。しかし、資産家一族においては、遺言書や遺留分侵害額請求といった法的要素が複雑に絡み合います。
不確実な相続手続きを円滑に進めるため、また、多額の資産を次世代に確実に承継するためには、税理士や弁護士などの専門家にできるだけ早い段階でご相談されることを強くお勧めします。
【関連記事:【専門家解説】相続の基礎知識完全ガイド|相続の流れから税務・手続きの基本まで】