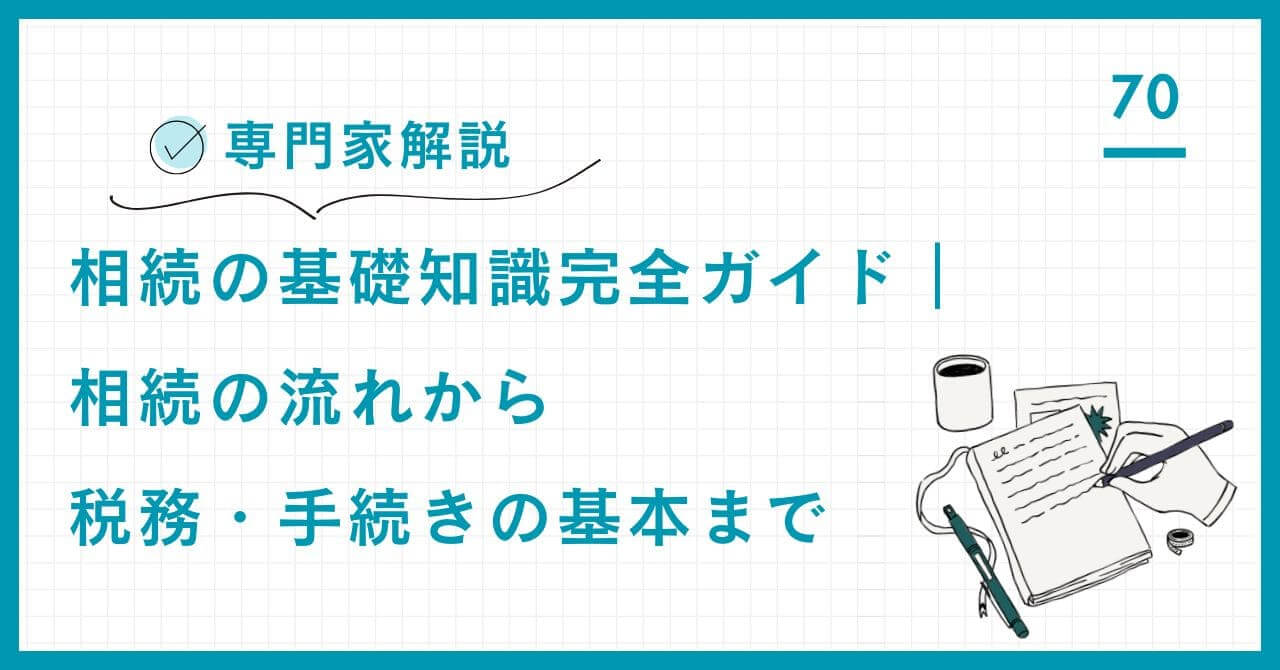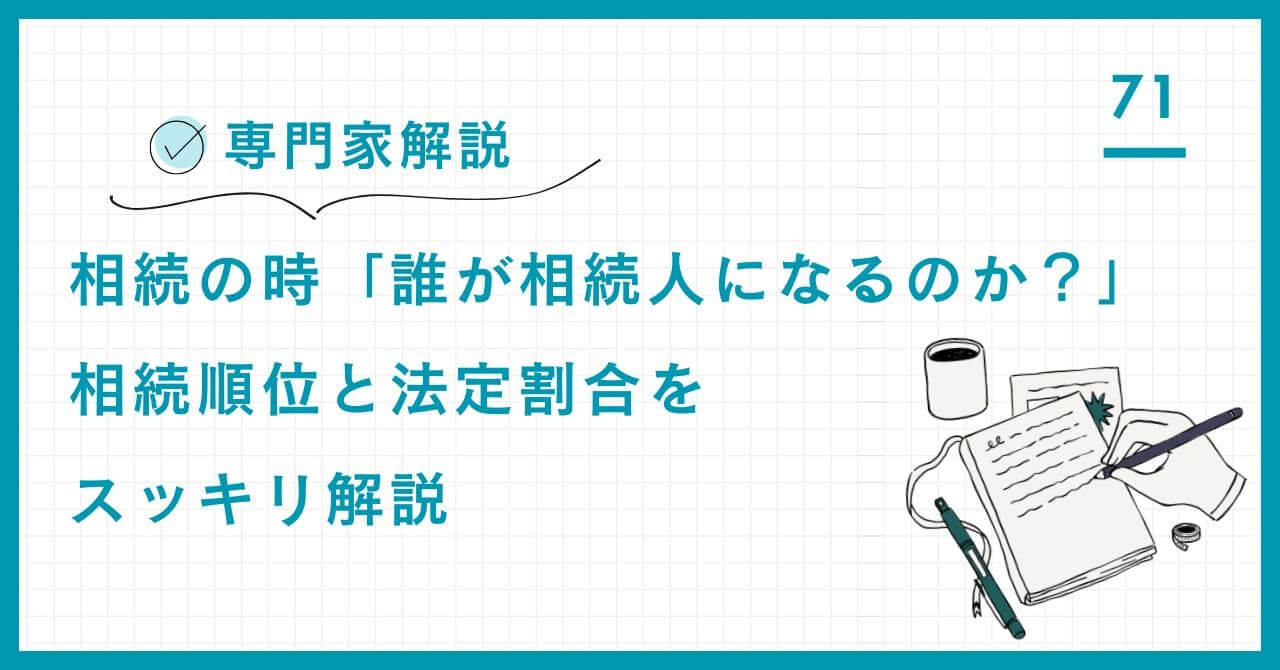相続が発生した際、まず最も知りたいのは「自分たちは相続税を納めなければならないのか?」「そもそも申告が必要なのか?」という点です。特に多忙な経営者や資産家の方にとって、煩雑な手続きに時間を割く前に、ご自身の状況を「ざっくりと、かつ正確に」把握することは、次に取るべき行動を決める上で不可欠です。
本記事では、相続の専門知識がない方でも、頭の中で簡便的に相続税の申告要否を判断できる3つの手順を解説します。この知識を身につけることで、不確実な状況に冷静に対処し、次に税理士に相談すべきタイミングを見極められるでしょう。
なお、本記事はあくまで「申告必要性の初期判断」を目的としたものであり、正式な相続税の申告要否は、財産評価・債務調査・各種特例の適用可否を踏まえ、税理士などの専門家による確認が必須です。
[ 目次 ]
1. 相続税の申告・納税の要否を判断する3つの手順(STEP形式)
相続のパターンは、「納税の必要なし」「申告の必要あり(納税なし)」「申告・納税の必要あり」の3パターンがあります。ご自身がどのパターンに当てはまるかを判断するため、以下の手順でざっくりとした計算を行いましょう。
1-1. 【STEP 1】遺産の総額を簡便的に計算する
まず、相続財産を全て足し合わせた「遺産の総額」を概算します。この段階では、厳密な評価は不要ですが、遺産は、現金・株式・自宅など、主要な資産を時価や固定資産税評価額を用いて合算し、土地は実売価格の8割を目安とします。
| 資産の種類 | 簡便的な評価方法 |
| 現金預金 | そのままの金額 |
| 上場株式 | 亡くなった日の終値 |
| 自宅の建物 | 固定資産税の評価額(納税通知書に記載) |
| 自宅の土地 | 実売価格の約8割(正しくは路線価ですが、概算用) |
実践例(試算):
現金2,000万円、株式1,000万円、自宅建物1,000万円、自宅土地(実売価格1億円)8,000万円の場合、合計は1億2,000万円となります。
1-2. 【STEP 2】「基礎控除額」と比較し申告の要否を判断する
相続税には基礎控除があるため、遺産の総額がこの控除額を超えなければ、相続税の申告や納税などを一切行う必要がありません。基礎控除は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円を加算して算出され、遺産総額がこれを超えたら、納税額がゼロでも申告が必要です。
- 算式: 相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 例: 法定相続人が配偶者と子の2人の場合、3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除額となります。
1-3. 【STEP 3】「配偶者の税額軽減」で納税の要否を判断する(概算)
STEP 2で申告が必要だと判断されても、すぐに納税が必要とは限りません。ここで「配偶者の税額軽減」の特例を活用した概算を行います。遺産の総額が1億6,000万円以内であれば、とりあえず配偶者がすべて相続することで納税額をゼロにできますが、この金額を超える場合は、申告・納税が必要となる可能性が高いと判断できます。
- 特例の基準: 配偶者が財産を相続する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税が課税されません。

2. 専門家が指摘する「ざっくり暗算」のデメリットと注意点(Q&A形式)
上記の方法はあくまでざっくり計算用の方法です。本格的な対策を講じる場合は、必ず専門家に相談が必要です。
2-1. Q. ざっくり計算で際どい金額の場合、どうすればいいですか?
A. ざっくり計算では、相続財産が基礎控除をギリギリ超えるかどうかの判定はできません。また、土地の評価額には小規模宅地等の特例など、税額を大きく減らす特例が多数存在します。これらの特例を適用するには厳密な計算と申告が必須です。計算結果が基礎控除額の1.5倍程度を超える場合は、特例を適用しても納税が避けられない可能性が高いため、早期に税理士にご相談ください。
2-2. Q. 配偶者控除を最大限利用すると、将来的に損をすることはありますか?
A. はい、その可能性があります。配偶者がすべてを相続することで、確かに今回の相続税(一次相続)はゼロになりますが、その配偶者が次に亡くなった際の相続(二次相続)において、相続財産が減らずに税負担が大きくなるケースが多く見られます。富裕層の資産承継戦略では、二次相続まで考慮し、あえて一次相続で相続税を支払っておいた方が、長期的には得になることがあります。
2-3. Q. 専門家を使わず自分で申告するデメリットは何ですか?
A. 自分でやる場合、手間がかかる以外にも、特例の適用漏れや計算間違いによって、節税し損ねるというリスクがあります。相続税は高額になることが多いため、税理士の報酬を支払っても、特例を適用して納税額を減らすことによる節税効果のほうが、はるかに上回る場合が多いです。
3. まとめ:不確実な状況には「迅速な専門家への相談」が鍵
本日ご紹介した方法でざっくりと計算していただければ、相続がおこった時に「何もしなくてもいい」のか「何かしなければならないか」のか程度は判断することができます。「何かしなければならない」(遺産総額が基礎控除を超える、または1億6,000万円を超える)場合は、できるだけ早く税理士などの専門家に相談し、アドバイスを受けながら進めていくことをおすすめします。
ご自身でやる場合は手間がかかる以外にも、間違えたり節税し損ねてしまったりするリスクがあるため、中立的な専門家を活用することが賢明です。
【関連記事:【専門家解説】相続の基礎知識完全ガイド|相続の流れから税務・手続きの基本まで】